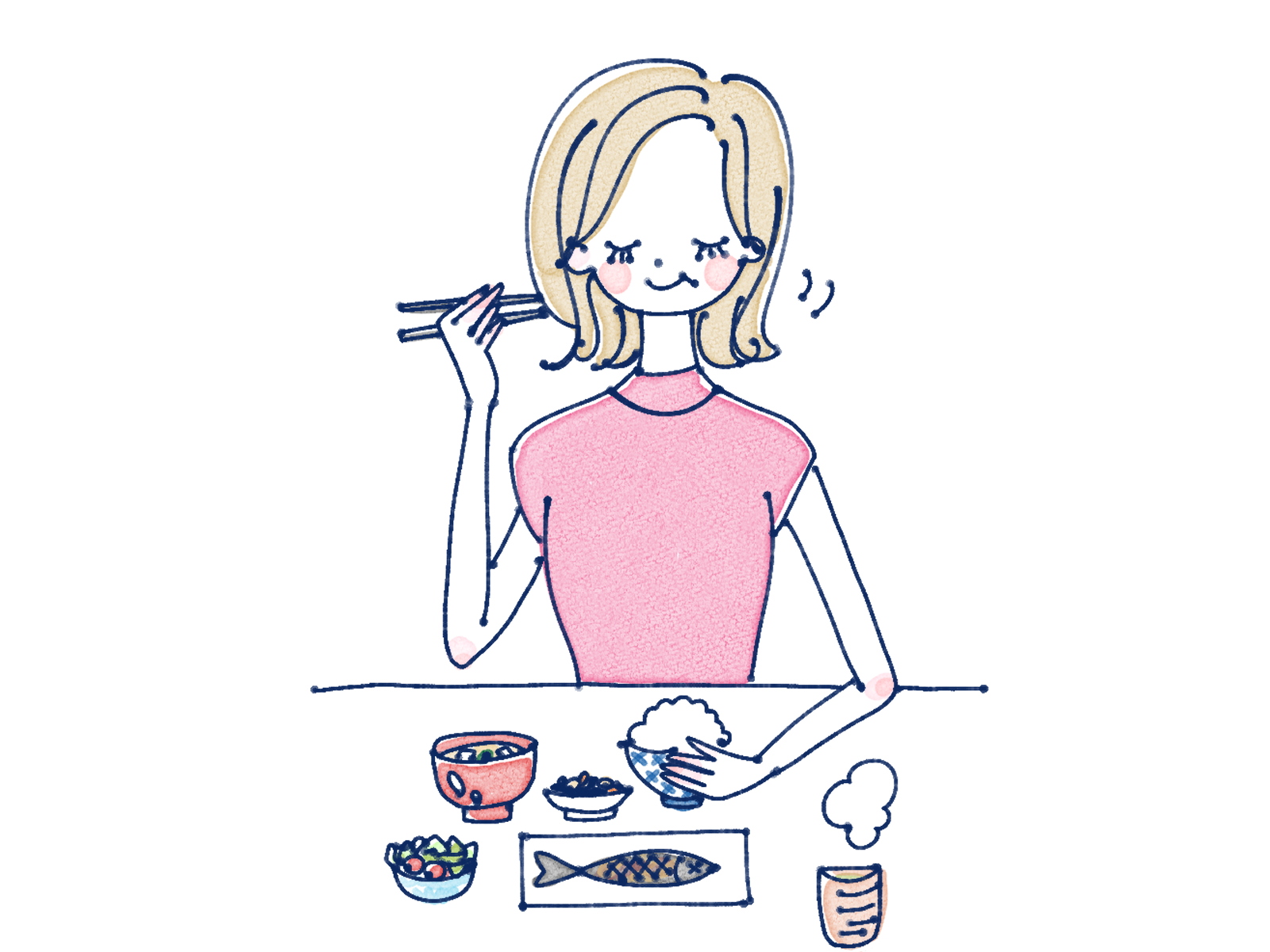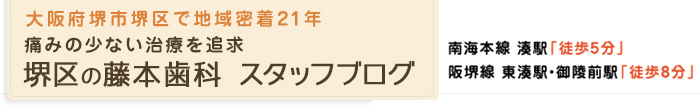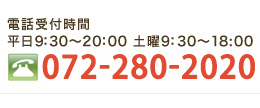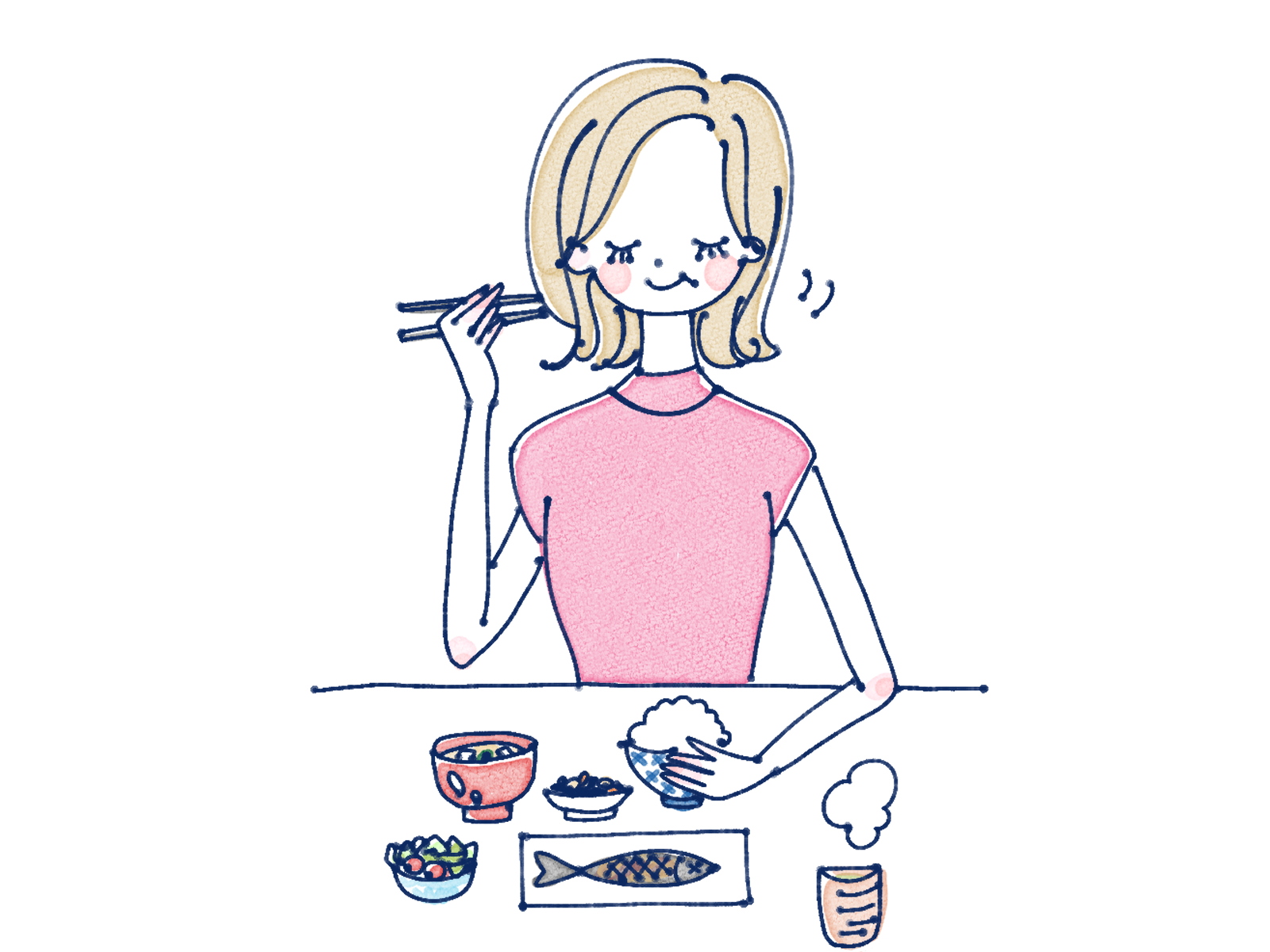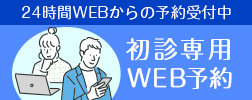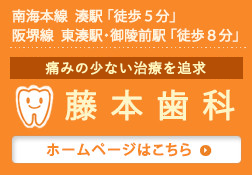歯と口の大事な役割
噛む、飲み込むことは栄養摂取の第1歩
生命活動の基本となる食物の摂取において自らかみ砕き飲み込んで栄養摂取することは大変重要です。口の機能として、残っている歯が多く、噛む力が維持されていることが大切です。
表情をつくる
笑顔などさまざまな表情は、口のまわりの筋肉や噛み合わせによって表現されます。
発音を助ける
言葉を発するときは、歯とくちびるや舌の動きを調和させて、発音しています。
噛むことで脳を活性化させる
噛む際にあごの筋肉を動かすことで、脳の血流改善や神経系が刺激されて、脳が活性化します。
歯と口の機能の衰えは全身の機能低下に
歯を失うなど歯と口の機能の低下は、ドミノ倒しのように全身の機能低下と認知症へとつながっていきます。歯を失うことで噛めない、飲み込みにくいといったトラブルから、食事の量が減ると食欲も低下して栄養不足となり、全身の衰えへと影響を及ぼしていくのです。
口と全身の病気
近年のさまざまな研究により、歯や口の中の状況が全身の病気と関連することが明らかになってきました。つまり、歯や口の中を健康にしておくことで、さまざまな病気の発症のリスクを下げることが期待できるのです。
(心臓病)
動脈硬化は、心臓に血液を送る血管が狭くなる「狭心症」や血管のつまりによる「心筋梗塞」を引き起こす原因となります。歯周病は動脈硬化を引き起こす要因の1つといわれています。
(糖尿病)
糖尿病は血糖値が高くなる病気です。歯周病菌による炎症物質は血液中のインスリンの働きを低下させ、血糖値をさげにくくすると指摘されています。また、糖尿病の重症化により、歯周病が悪化することもわかっています。
(認知症)
認知機能の低下は、さまざまな発症因子で引き起こされます。なかでも、必須アミノ酸やビタミンをバランス良く食事の栄養として摂取することが大切です。噛む力と歯の噛み合わせを維持することで、発症因子を抑制剤することがわかってきました。また歯周病の影響による動脈硬化によって、血管性認知症のリスクも高くなります。
歯周病菌は、歯と歯茎の境目に付着した歯垢の中にいます。
この菌が歯茎に炎症を引き起こし、炎症が進行すると歯と歯茎の間の溝が深くなり、さらに深くなると、歯を支える骨が破壊され重症化し、歯がぐらぐらしてきて、結果的に抜け落ちてしまいます。
歯周病菌などの細菌は、口の中に残っている食べかすの糖分などを栄養にして増殖します。毎日の歯磨きが何より大切ですが、歯周病の軽度の段階では自覚症状がほとんどないので、定期検診による早期発見、早期治療が大事です。
●歯周病セルフチェック●
□歯ぐきに赤く腫れた部分がある
□口臭がなんとなく気になる
□歯ぐきがやせてきた
□歯と歯の間にものがつまりやすい
□歯を磨いた後、歯ブラシに血がついたり、すすいだ水に血が混じったりすることがある
□歯が浮いたような感じがする
□歯ぐきからウミが出たことがある
✔️チェックが1~2個
歯周病の可能性があります。歯磨きの仕方を見直すと同時に、歯科医師に相談しましょう
✔️チェックが3個以上
軽度あるいは中等度歯周炎以上に歯周病が進行している恐れがあります。
早めに歯科医院を受診しましょう