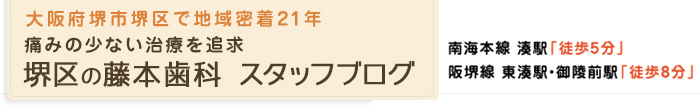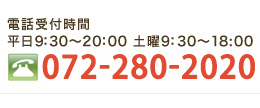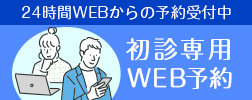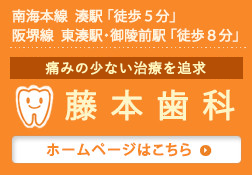①抜歯後の出血が止まらない
抜歯後に少量の出血があるのは、特に問題ありません。しかし、いつまでも出血が続く場合は、局所的・全身的な原因によるものがあります。
局所的な原因・・・歯の周りの粘膜の損傷、歯の周囲骨の骨折、骨内の血管損傷、歯の周りの肉芽組織を取り除く処置が不十分な場合もあります。
全身的な原因・・・血液疾患、肝疾患、抗凝固剤や血小板剤の内服などがあります。
抜歯後に出血が止まらないからといって、強くうがいをするとかえって出血をうながしてしまったり、血餅(けっぺい)という傷口を塞ぐ役割をしてくれるかさぶたのようなものが取れてしまい、治癒を遅らせてしまう原因になってしまいます😱
清潔なガーゼなどを丸めて15分〜20分程度強く噛み、圧迫して止血を行います。それでも止まらない場合は、歯科医院での止血処置を受けてください。
また、前述した疾患や服薬しているものがあれば、必ずお申し出ください。
②抜歯後の痛みが治まらない
通常、痛みは抜歯後24時間以内に軽減しますが、2日目以降にも痛みが続く場合は歯の破折片の残存、抜歯した付近の骨の亀裂、骨折、隣の歯の脱臼などが考えられますが、抜歯後3日以上経ってから痛みが強くなった場合は、抜歯後の細菌感染、ドライソケット(抜歯後の傷に血のかたまり(血餅)がなく、傷口が露出した状態になり、強い痛みがある状態)の可能性がありますので、歯科医院へ受診してください。
細菌感染の場合、抗生剤を服用していただき経過を見ます。
③抜歯後の腫れが強くなった
乳歯や揺れているはの抜歯では、腫れはほとんど見られませんが、埋伏歯(歯肉に埋まった歯)や親知らず(特に下顎)の抜歯後では、抜歯後2〜4日で腫れが強くなることが多いですが、その後徐々に腫れは減少していき、1週間ほどでほとんどなくなります。
腫れは抜歯後の炎症により出現しますので、処方された化膿止め(抗生物質)などを必ず服用しましょう。
また、飲酒、長風呂、運動などは避け、冷やしたり温めたりすることもよくありません。
十分に注意をしていても、細菌感染、全身疾患により治癒が遅れる場合もあります。
もし抜歯後に何か変化などがある場合は、必ず歯科に受診しましょう!!